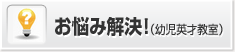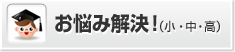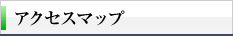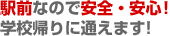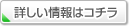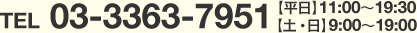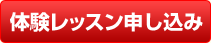12月出版の拙著8作目より一部抜粋です②2025年11月19日
12月出版の拙著8作目「早慶筑波に合格は非認知能力で決まる」より一部抜粋です②
●中学受験、高校受験、大学受験で求められるのは認知能力(一般入試の場合)
一般入試の場合、中学受験では主として国算理社の4教科、高校受験では主として英数国の3教科、私立大学の一般入試では主として英語プラス主要教科で得点力の争いとなります。あくまで認知能力の相対評価で受験者の合否が決定します。
ある意味、主観的要素が排除され、学力以外の他の要素が合否を動かすことがないため、極めて公平な選抜方式だといえると思います。
要するに、「勉強さえできれば合格!」という認知能力の高さだけを見極める、極めてシンプルな診断が学校によりなされるわけです。それが中・高・大学の一般入試の特色です。
●小学校入試における、認知能力と非認知能力の比率配分表
一方で小学校受験こそ非認知能力が重要です。
なぜなら小学校という環境は、まだ精神的に未発達な児童を預かって教育をする場ですから、基本技能(お友だちと仲良くできて、人間関係を円滑にできる)などが入試によって判断されるのです。わが子の非認知能力は、入試時に主に行動観察試験で測られます。
●非認知能力が高い子は、小学校受験に合格する子
幼稚園でのグループ活動で、失敗があったようなときに、「だめじゃないか! そうじゃないよ!」と感情的に口から出てしまう子は、「精神的に安定している」や「感情のコントロールがうまい」という項目の反対です。非認知能力が低い子と判断されるでしょう。
一方で、「ごめんね。もういっぺんやってみようよ」といえる子は「人間関係を上手に築くことができる」や「問題解決能力に優れる」項目と合致する子です。
「それもいいけど、こっちの案でやってみない?」といえる子は「共感力が高い」や「創造性が高い」に当てはまります。
「来週の発表会までに、もう1枚大きな絵を完成させようよ」とイニシアティブを発揮できる子は「主体的に行動ができる」し「目標を設定し、達成する粘り強さがある」子です。
ほーら、ですから、幼稚舎や早実に合格できる子は「非認知能力が高い子」なのです。それは早慶に限らず、その他すべての小学校の入試での、重要な採点項目となります。
だって、人間関係を上手に築けるよい子は、どんな学校だって欲しいはずですから。
●非認知能力を高めると、わが子の将来の収入が高くなる
幸せをどのように感じるか? 社会的成功? 名声を得ること? 組織で昇進すること? 社会的成功の1つの基準として収入・年収が挙げられるかもしれません。
現在、経済学の分野でも認知能力と非認知能力の研究が進んでいます。非認知能力のある部分をトレーニングにより伸ばした実験集団と、そのトレーニングを受けなかった集団とを比較したときに、将来の収入で明らかな差(実験にもよりますが、数値的に平均で7%から35%)が生じている、という研究成果が世界中の論文で報告されています。
もちろんトレーニングを受けた人たちの収入が高いのです。端的に言うと、「非認知能力を高めるとわが子の将来の収入が高くなる」ということです。




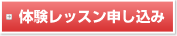
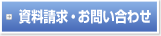
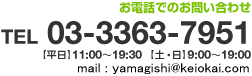

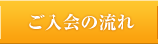
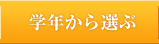
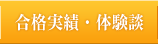
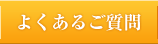
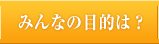

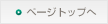
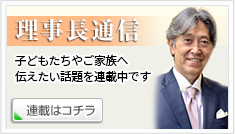


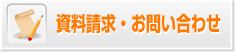
 ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから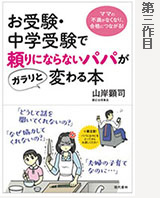 ご購入はこちらから
ご購入はこちらから