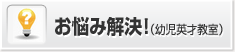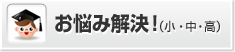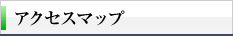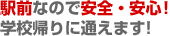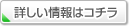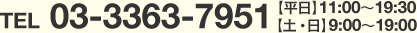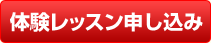12月出版の拙著8作目より一部抜粋です①2025年11月12日
12月出版の拙著8作目「早慶筑波に合格は非認知能力で決まる」より一部抜粋です①
●非認知能力とは、ものすごく大雑把に定義すると「人間力」
認知能力とは、数値で測れる能力です。
「認知能力が高い」とは、もっともシンプルに言うと「学力が高い」ということです。さらにシンプルに言うならば、高学歴の人は認知能力が高い、と考えていいでしょう。
一方で近年、注目度の高い非認知能力に関しては、私は「感性と言語と行動の力が高い」と理解しています。
非認知能力とは、数値で測れない能力です。
「意欲」「忍耐力」「自制心」「協調性」「自己肯定感」「コミュニケーション力」「目標達成力」「問題解決力」「想像力」「独創力」など、子どもの将来の成功や幸福感に影響を持つ力の総体です。
言い換えると、「精神的に安定している」「自己肯定感が高い」「感情のコントロールがうまい」「主体的に行動ができる」「目標を設定し、達成する粘り強さがある」「共感力が高い」「人間関係を上手に築くことができる」「創造性が高い」「問題解決能力に優れる」などです。総じていうと「人間力が高い」と考えていいでしょう。
非認知能力を高めると、わが子の将来の収入が高くなるという研究も多くあります。
これら個々の能力は、学力の高さで測れる認知能力とは性格を異にしています。能力や知能の使い方の分野が違います。
ですから、社会に出てからの成功の度合いを高めるには、高学歴を持つ(認知能力が高い)だけではなく、非認知能力も同時に高めることが必要なのは明らかですね。
わが子が幼稚園から小学校に進む過程で、お友だちと協力しながらさまざまな達成をするうちに、「共感力が高まり」「人間関係を上手に築くことができる」ように成長してきます。それらは「精神的に安定して」いて「感情のコントロールがうまい」状態でしょう。
家庭内だけでなく、一歩社会へ踏み出した環境、たとえば幼稚園はわが子が非認知能力を高めるトレーニングの場です。
家庭内でも家庭外でも、わが子が経験を積み、成長してくると、善悪の判断に長けてくるようになります。すると、大人に叱られることが少なくなってきます。結果として「主体的に行動ができる」機会が増えてきます。
また、ときとして失敗もするでしょうが、成功体験を積み重ねていくうちに、「目標を設定し、達成する粘り強さ」も強化されていきます。
非認知能力は経験を通じて伸びる能力なので、大人になっても伸び続けます。
外国語の発音のように、敏感期(ヒトの場合、6歳から10歳ぐらいまで)までに獲得しないと、母国語にない「子音」の発音を聞き分けて発音することが難しい、という能力よりも、はるかに発展性が高いのが非認知能力です。




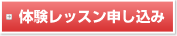
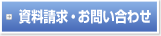
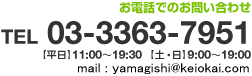

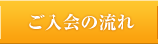
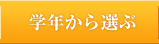
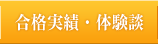
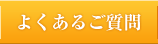
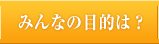

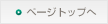
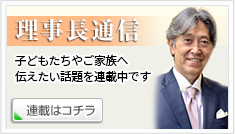


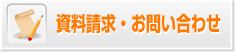
 ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから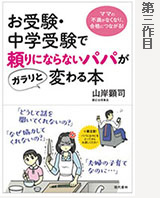 ご購入はこちらから
ご購入はこちらから