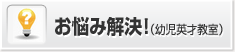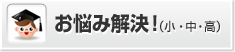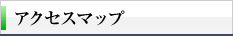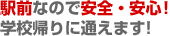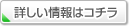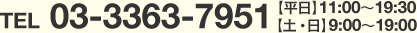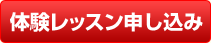前回よりつづき2025年8月20日
前回よりつづき
受験も原理は同じ。だから早くから気づいた親は有利なんです。学校の出口である大学(修士、博士はまた別)で、受験で成功したいと希望するならば、大学入試で一発合格を目指すより、付属高校から入学する方が一般的にはハードルが低いものです(付属高校が存在するならば)。
ごくごく単純化した言い方をするならば、東大に入学する人は毎年約3000人いますが、そのほとんどは東大が第一志望の人です。国公立大学医学部が第一志望だけれど東大理Ⅲは無理なので理Ⅱにした、とか千葉大医学部にした、とかいう屁理屈は抜きにして。
そして東大合格は及ばなかったけれど高い学力を持つ受験者は、涙を呑んで早慶に入学します。早大、慶大の入学者の約半分は、東大に不合格だった人です。細かな条件で数字を検証すれば微細な違いはあるでしょうが、大雑把な表現でいうとそのようなものです。
慶応義塾大学への入学者は毎年約8000人、早稲田大学への入学者は約13000人いますが、そのうちの半分とは言わずとも6、7000人ぐらいは東大に落ちて(もしくは東大受験をあきらめて)、泣く泣く早慶に入学してきた人です。厳密に言えばいろいろ検証の対象はありますが、ざっくりと申せばそのようなものです。一つの例えですからね、あんまり揚げ足をとらないように。
大学入試は全国レベルの受験大会ですからね。地方出身の優秀な高校生は、地元を抜け出して東京に住むには大学受験で最上位の学校に合格する以外に方法がない! とまなじりを決して日々、過去問を攻略しているのですから、東京でのほほんとバカ高校生暮らしを満喫していた連中が大学受験であっさりとうっちゃりを食らうのは目に見えています。
それだけ厳しい大学受験を避けるならば、付属高校があるならばそこを攻略して大学への推薦を狙った方が確実、という考えもあります。そこに気づいた親と受験生は、大学受験を避けて、高校での付属校合格を狙うでしょう。
なおそれよりも付属中学から入学する方が、受験の競争は緩い可能性があります。まして小学校受験は、わが子の資質や適性により、思いがけずに最難関小学校に合格できる可能性もあります。と、どんどん受験学齢が下がってくるわけです。
逆の道の辿り方もあります。「わが子が7歳から12歳までの学童期に、志の高い家庭で育つ子どもたちと切磋琢磨できる環境を整えたい」と願う親ならば、小学校受験は必須でしょう(ブランドだけが目的、なんていう親は、志に難がありそうですけれど)。
しかし、わが子の適性や能力が第一志望校に必ずしも合致するとは限りません。きちんとしたやり方で準備をしたとしても、わが子の適性と合致したのは第三志望の小学校だった、という結果であるかもしれません。その場合、小学校受験で目標が手に入らなければ中学受験で目標に到達する、という考えもあります。たとえば早慶が目標であるならば、大学までには中・高と段階を踏んでチャレンジすることができます。そして早い段階で気が付いて準備を始めた親も子も、チャレンジする機会が増えます。
わが子の道はどこへと続いていくのでしょうか? しっかり自立するところまでは親の役目ですね。




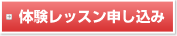
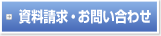
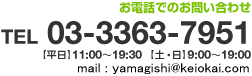

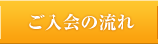
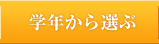
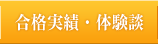
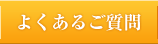
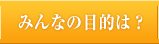

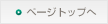
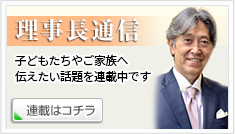


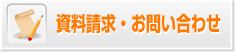
 ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから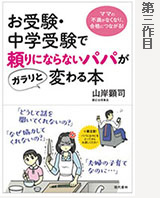 ご購入はこちらから
ご購入はこちらから