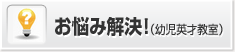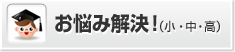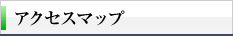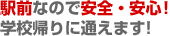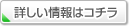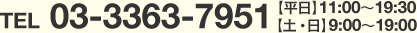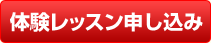ミラノ冬季オリンピックが終了しました。2026年2月25日
ミラノ冬季オリンピックが終了しました。オリンピックはトップアスリートにとって4年に一度の大イベントです。言うまでもなく、その時期の、特定の数日間に合わせて最高のコンディションで迎えないとメダルに届きません。競技の技能以外にも、無数にクリアしなければならない条件があります。
そもそもオリンピックに出場できるだけでも大変なハードルを越えなければなりません。オリンピック選手選考会の直前まで不調だったアスリートが、選考レースで勝利し参加権を獲得することもあれば、その真逆で実力者が参加を拒まれることもあります。
運ですね。運としか言いようのない清々しさと残酷さがあります。
私は冬季オリンピックを見るたびに思い起こす人がいます。スキー女子モーグルの第一人者であった上村愛子選手です。初出場から4度もオリンピックに出場し、そのたびに7位、6位、5位、4位と順位を上げながら、最後までオリンピックのメダルに届きませんでした。しかし彼女は世界選手権では何度も優勝し、3度目と4度目に出場したオリンピックの間には2度も年間チャンピオンになっています。どれほどの自己研鑽と努力を積み重ねてきたことでしょう。彼女の悲運には深く無情を感じるところがあります。
人はうまく事が運ばないと、そこに固執することがあります。私にもあります。私は趣味の幅が比較的広く、相互に関連しそうもない分野のことにも興味を引かれる者です。
おまけに興味を持った分野は短期間で知識を深めることができるよう探求に励みます。ところがですね、何年かけてもまったく進歩も上達もしない分野があります。だれにもそういうことはあるかもしれませんが、長期間倦むこともなく、興味を持って取り組んでいるのにさっぱり成果が上がらない、というものです。
私の場合は楽器の演奏ですね。ヒドイ。レッスンをしても、もはやデイケアに出かけて指先の機能のリハビリをしているに過ぎないほどです。
それでも固執しています。いつかあの、あこがれのミュージシャンのように、自らの演奏に陶酔できる瞬間がくるのではないか(いや来ない)と夢想しながら。
そういう状況であるならば、そのエネルギーを他の分野、もっと目に見える上達や達成が実感できることに集約すれば良くはないか? 長所を伸ばす方が効率よく自己実現できるのではという疑問も湧くのですが、苦手を克服するために努力を重ねる習慣を身につけることが一つの目的でもありますから。
そもそも多趣味な人間は内から湧き起るエネルギー量が豊富ですから、とんと「うだつ」の上がらないことにエネルギーを消費したとしても、それで枯渇するわけではないのですね。もうライフワークです。
英語、もしくは英会話、あるいは外国語習得というのも多くの日本人にとって課題であり難関であり、目の上のタンコブですね。受験教科でもありますし、逃げられない修業のひと つです。
すべての言語は母音と子音の発音とリズムと抑揚と音の強弱で構成されますから、歌と一緒です。特に幼児期から敏感期は母国語を修得するために耳が敏感です。その時期を外すと外国語をネイティブのような発音で発することは難しくなります。流ちょうにしゃべれるようになるにはその時期のトレーニングは貴重です。
しかしながらその時期は母国語で思考する力を高めなければならない時期ですから、母国語と外国語を同時に高度に身につけるためには、ここで紙幅を割くことが不可能なほど多くの条件をクリアし環境を準備しなければです。次回は才能の話に復線します。




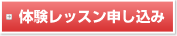
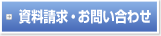
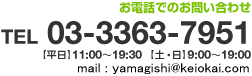

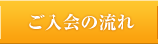
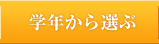
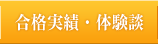
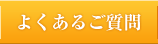
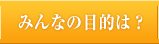

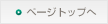
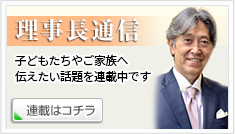


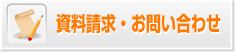
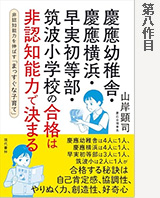 ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから ご購入はこちらから
ご購入はこちらから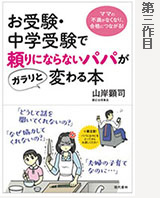 ご購入はこちらから
ご購入はこちらから